2001年08月31日発行703号
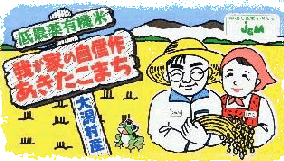 【阿部淳の『あぜ道だより』――秋田県大潟村から「出穂期」 |
私の住む大潟村は今、田んぼの「あきたこまち」が稲穂を出す「出穂期」を迎えています。日本海がすぐ近くにあるので毎日と言っていいほど風が吹きます。青空の下、風になびく稲穂を見ると何とも言えずほっとした穏やかな、そしてここまで稲を育ててくれた自然に感謝したい気持ちになります。このころ田んぼに行くと時折かすかにご飯の匂いが香るのもこの季節の風物です。 稲と言う植物はその年の条件で多少の差は有りますが、発芽してから穂が出るまでだいたい十三枚から十五枚の葉を出します。最後の葉を「止葉」と言うのですが、その葉が開いてから稲穂が出てきます。ひとつの穂には百粒前後の花が付きますが、穂の先から順番に白く小さな花を開花させ、咲き終わるまで一つの穂で五日から十日ほどかかります。ただ、不思議なことに必ず最後に咲く花は上から二番目の花なのです。 さて、花が実(籾)になるため受粉・受精はと言うと、稲は自家受粉のため風や虫など他の力に受粉を依存しなくてもよいのです。そのために開花時間はとても短く、受粉も開花直前に終わっているのが特徴です。そして、花粉の寿命もとても短くて三分ほどから長くて六十分と言われています。したがって、受精も一時間あまりで終えるのです。ちなみに稲の花は午前九時ころから咲き始めて午後二時ころには閉じてしまいます。 あと一か月足らずで田んぼは「黄金色」になりますが、こうした稲の絶妙な生態ひとつ知るにつけても遺伝子組み換えなどの技術で自然の摂理に手を加えるべきでないと強く思います。大事なことは自然の摂理をどのようにうまく活用して生かされていくかであり、その事にこそ知恵を働かすべきではないでしょうか。 |