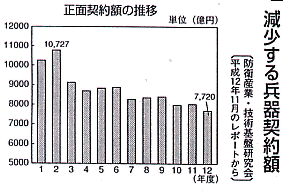2004年02月13日発行826号
【「武器輸出3原則」見直しが噴出 武器輸出国めざす軍需産業】 | ||
武器禁輸から「死の商人」へ「武器輸出3原則の見直し」を求める声が政府・自民党から公明党、はては民主党からも上がっている。「国是」としてきた武器禁輸政策を完全に撤廃し、日本を武器輸出国家=「死の商人」に転換させる動きが急激に強まっている。 昨年12月19日、小泉内閣は米国が開発したMD(ミサイル防衛)システム(イージス艦発射スタンダード・ミサイルや地上発射のパトリオット・ミサイル)の2004年度からの導入を決定した。 これに関連させて3原則見直しが噴出。福田官房長官は、迎撃ミサイルの技術開発部品について「武器輸出3原則があるので、米国と交換や提供ができないのは問題という議論がある。今後3原則の見直しを検討する」と表明した。 1月に入ると、石破防衛庁長官が「兵器の共同開発を米国以外にも広げることを検討する」として武器輸出3原則の抜本的見直しまで示唆しだした。 武器輸出3原則とは、政府の基本方針として表明されたもの。67年に佐藤首相が「(1)共産圏(2)国連が禁止した国(3)紛争当事国への武器輸出禁止」を表明。76年に三木首相が上記の3地域以外の国であっても全面的に武器輸出を「慎む」という政府統一見解を出し、この時点であらゆる国に対する武器輸出が禁止された。 自民党などが「問題」としているのは、共同研究で日本が分担したミサイル技術を、日本で生産しても米国に輸出できないということだ。認められているのは技術供与だけで、武器(武器の部品含む)製品の輸出は禁じられている。せっかくの研究が実を結ばないという論法だ。 軍需企業が見直しを要求3原則の見直しを最も強く求めているのは日本の軍需企業だ。 MDそのものは、米国防総省と米軍需独占体が莫大な費用を要するミサイル迎撃システムを日本・韓国に売りつけるプロジェクトである。日本の軍需企業がMDの共同研究に参画したのは、MD特需と共同研究の実績を3原則のタガを外すテコに利用しようと狙ったからだ。 すでに95年6月、日本防衛装備工業会(三菱重工など131社)は、米国向けの武器輸出を解禁するように政府に陳情。96年には、日本の主要軍需企業と米国のボーイング、ロッキード・マーティン、レイセオンなど巨大軍需企業が日米安全保障産業フォーラムという組織を作った。日米の軍需産業で共に声を上げ、軍需産業を縛る政策の撤廃を求めるためだ。02年12月の同フォーラムの共同宣言は、日本政府に3原則見直しを求めている。 戦争支持する日本経団連
「冷戦」の崩壊以降、全世界的に兵器に対する需要は急速に縮小している。世界の軍需産業は生き残りに必死だ。 日本の軍需企業も、MDなど米国との共同生産を通じて、武器販売市場を世界に広げることを狙っている。これを許せば、米国のように常に軍需を維持・拡大するために世界中に紛争介入や戦争を求め、そうした政策を政府に要求する強大な戦争社会システムを日本の中に作り出すことになる。 1月13日、日本経団連の奥田会長がイラクへの陸自派兵を支持する見解を表明した。これは、海外派兵による日本の権益防衛とともに恒常的な軍需の維持を求める声が財界に強まっていることの表れである。3原則見直し論の背後にある戦争推進路線を封じることが緊急に問われている。 |