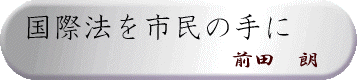| |||
ラッセルの呼びかけに応えたのは実存主義哲学者のジャン・ポール・サルトルであった。 ラッセルが国際戦犯法廷を呼びかける少し前のことになるが、コーネル大学から招請を受けたサルトルは、アメリカによるヴェトナム北爆を理由にアメリカ訪問を拒否していた。 フランス植民地主義を徹底して批判し、フランツ・ファノン、エメ・セゼール、アルベール・メンミ、パトリス・ルムンバらとともに現代史を闘ったサルトルがラッセル法廷の執行裁判長となった。思想を生きぬき、現実と格闘し、「時代との婚姻」を引き受け続けた<アンガジュマン>は、ラッセルの挑戦を正面から敢然と受けて立ち、自らの闘いを完遂することになる。 1967年5月2日、ラッセル法廷開廷にあたり、サルトルはニュルンベルク国際軍事裁判に言及し、ニュルンベルク裁判が国際法の地図を塗り替えたことを確認するとともに、ニュルンベルク裁判の限界をも指摘したこの時、凡百の評論家とは異なって、サルトルはニュルンベルク裁判の限界を指弾することではなく、その発展をいかに実現するかに焦点を当てた。 「ナチを裁くために創られた組織が、その独自の役目を終えたのちも存続していたら、つまり、国際連合が、行われたばかりのことからあらゆる結果をひきだし、総会での票決によってその組織を強化して常設の『法廷』とし、戦争犯罪に関するあらゆる告発を識りかつ裁く権能をそれにあたえていたら」。 ニュルンベルク裁判の後の空白を、国連が放置してきたその空白を埋めるために開かれたラッセル法廷の場でサルトルは、民衆法廷の本質に迫る。 「『ラッセル法廷』は、この二重の矛盾した確認から生まれました。ニュルンベルクの判決は、戦争犯罪について調査するための、また必要ならそれを裁くための、制度機構の存在を不可欠のものとした、にもかかわらず、どの国の政府も人民もそれを創りだす力を持っていないという現状、この二重の確認からです。われわれは、誰からも委任されはしなかったのだということをはっきりと自覚しています、それなのに集まろうと提唱したのは、誰もわれわれに委任することなどできないのだということも知っていたからです。なるほど、われわれの『法廷』は制度機構ではない。が、だからといって、制度化されたどのような権限にもとってかわるものではない。それどころか、それは、ある空白とある請求に由来するものなのです。われわれは、諸政府によって集められた現実の権限を付与されたわけではない。しかし、さきほど見たように、ニュルンベルクでのこの権限付与は、異論の余地ない正当性を司法官にあたえるに十分ではなかったのです。『ラッセル法廷』は、これに反して、みずからの正当性は、その完全な無力に、と同時に、その普遍性に起因するのだ、と考えています。」 民衆法廷にはいかなる実力もない。もし実力を行使できれば、それは言葉のもっとも悪い意味での「人民法廷」、つまり「リンチ裁判」になりかねない。民衆法廷にはいかなる権威もない。誰からも授権されていない。 しかし、この無力と無権威こそ民衆法廷の真義であることを、サルトルは最初から見抜いていた。 「われわれは無力です。これがわれわれの独立の保証なのです。われわれをたすけてくれるものはなにもありません、われわれ自身とおなじように私人の集まりである支援諸組織の協力をのぞいては。われわれは、政府代表でも党代表でもないので、命令を受けることなどできない。われわれは、いわゆる<良心にしたがって>、あるいは、そう言ったほうがよければ、精神のまったき自由において、事実を検討するでしょう。」 (参考文献)ジャン・ポール・サルトル『植民地の諸問題』(人文書院、2000年)
|