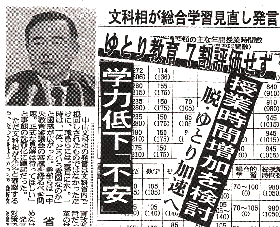2005年03月04日発行876号
【脱ゆとり教育の真相 / 「学力低下」批判を利用 / 公教育解体の促進狙う】 | ||
「総合学習」を見直し、授業時間を増やす−−文部科学大臣の相次ぐ発言は「学力低下を不安視する世論に押された文科省の路線転換」として報道されている。真相は違う。「ゆとり教育」の本質である公教育切り捨て路線には何の変化もない。むしろ「学力低下」批判を利用する形で、より強力に推進されようとしているのだ。
「学力低下」は国策はしごを外された観のある学校現場の混乱をよそに、世間では「脱ゆとり教育」のムードが作られつつある。見直し論議に火を付けた中山成彬文科相はこう語る。「私はゆとり教育が学力低下の原因の一つかもしれないと言っている。授業時間がだいぶ減っており、学力が上がるわけがない」(1/18) 事実の指摘としてはそのとおり。だが、文科相やマスメディアが唱える「ゆとり教育悪玉論」に組みするわけにはいかない。彼らは肝心な部分をごまかしている。 授業時間やカリキュラムの削減は、公教育切り捨てという独占資本の要求に応えての国家政策であった。つまり、「学力低下」の主犯は独占資本なのである。 有名な事例をあげておこう。教育課程審議会の会長だった三浦朱門の発言だ。「学力低下は予測しうる不安というか、覚悟しながら教科審をやっとりました」「できん者はできんままでけっこう。限りなくできない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養っておいてもらえばいいんです」 教育予算を抜本的に削減するために、教育内容を切り下げる−−これが独占資本の基本戦略である。その結果、「学力低下」が生じても構わないと彼らは考えた。企業側からすれば、子どもたちの大半は将来の使い捨て労働力にすぎないからだ。 京都経済同友会は、中学校の義務教育廃止を求める提言(2000年)でこう述べる。「勉強嫌いをいつまでも学校に引っ張り、やる気と自信を失わせ、いたずらに不登校を増やし、教師に苦労をかける無駄は、十二歳で打ち止めとしたい」 公教育を「無駄」とみなす財界の本音があらわれた一文といえよう。 差別・選別を徹底義務教育費国庫負担金廃止の動きを見れば明らかなように、独占資本にとって公教育はあくまでも切り捨ての対象である。「学力向上」のために公教育の充実を図るなんて考えていない。 一連の「脱ゆとり教育」議論は路線転換ではなく、公教育解体を加速するためのキャンペーンみるべきだ。実際、「ゆとり教育」批判の大半は「現在の画一化した教育では学力向上は望めない。できる子をもっと伸ばすシステムが必要だ」というように、教育への競争原理導入という文脈でなされている。 文部科学省があげる「学力向上」策をみても、習熟度別学習の促進や学校選択制・小中一貫校の導入など、「教育の機会均等」原則を放棄する政策が並んでいる(「総合学習」の見直しは、脱ゆとり教育を世間にアピールする象徴的な意味合いが強い)。 財界団体は、よりストレートに市場原理下での競争=差別選別の徹底を打ち出してきた。日本経団連が今年1月に発表した提言は、「社会全体の教育力を向上させる」方策として、株式会社による学校設立や学校運営の民間委託、学校の成果に応じた補助金分配などを求めている。 「受け手のニーズに対応した教育」と言えば聞こえがいいが、要は「学力向上もカネ次第」ということにほかならない。教育費の自己負担増に耐えられない層は、最初から切り捨てられている。 意欲の低下こそ問題国際的な学力調査の結果をみると、日本の子どもたちは確かに深刻な状況にある。ただし、それは各国と比較した日本の順位やテストの点数ではない。本当の危機は学習意欲の著しい低下にある。 「国際数学・理科教育動向調査」(2003年)によると、日本の中学2年生で「数学の勉強は楽しい」と答えたのは39%。各国平均の55%を下回った。嫌いでもががんばれる目標があればまだいいが、「希望の職業に就くために数学で良い成績を取る」は95年の55%から47%へとダウンした。これは各国平均(73%)からすると、きわめて低い数値である。 これらのデータは、子どもたちが勉強する動機を持ちにくくなった日本の社会状況を物語っている。独占資本が進める雇用の不安定化は若年層を直撃し、彼らから安定した仕事を奪った。学校で熱心に勉強したところで、まともな就職に結びつく保証はなく、将来の展望を見いだせない。子どもたちの多くが「勉強しても仕方がない」と考えるのは当然であろう。 日本の子どもたちの「学力低下」の根本原因はここにある。主犯はやはり、目先の利益しか考えないグローバル資本主義なのである。 (M) |