2020年06月26日 1630号【コロナ禍の混乱に声上げた親 障害児放課後等デイサービスの時間延長 支援者とともに要求し実現 大阪市】 |
障害児親子直撃したコロナ 対市要請に立ち上がる大阪市在住の高橋瑞枝さん、浩一さん夫妻の子どもは特別支援学校高等部に通う重度自閉症児。強度の行動障害があり突発的な行動も多い。夫婦ともに介護職で、仕事を休むのは容易ではない。新型コロナウイルスで支援学校が休校となり、通っていた放課後等デイサービスには行けなくなった。他の事業所を利用せざるを得なくなり、日々の困難は増えた。支援学校への登校は6月1日開始。デイサービスの利用時間制限による日常生活の困難は今後も続く。 そこで、利用時間の追加と、障害者の移動支援事業で下校送迎を認めることを求めて5月29日、高橋さんらは平和と民主主義をともにつくる会・大阪(山川会)の支援者6人とともに、大阪市に対して「放課後等デイサービス・移動支援利用の柔軟な対応を求める要望書」を提出した。市の担当者は、その事業所に対して利用時間を配慮するよう提案することを約束した。 6月4日、市から高橋さんに電話がかかる。「当該の事業所に対して、匿名で利用時間についての配慮の要望があった旨を連絡し、学校短縮授業の開始に合わせて要望があれば18時まで利用を受け入れるとの回答を得た」と報告があった。要請行動が道を開いた。 大阪維新の府市政に振り回され、学校も福祉現場も大混乱。請願や要望という形で申し入れ、声を上げたことで、高橋さんと山川会は障害児施策や教育をめぐって行政を変えていける確信をつかんだ。高橋さんに思いを寄せてもらった。 みんなで手を尽くせば声は届くんだ(高橋瑞枝)各方面に数々の混乱をもたらした3か月の長期休校は、重度自閉症と強度行動障害を併せ持つ息子にも多くの困難をもたらした。3月に休校が始まり、デイサービスの事業所が午前10時からしか利用できなくなり、毎朝スクールバスを利用する生活サイクルが崩壊。朝起きられなくなり、本人は休校理由が理解できずに心身のバランスが乱れ、毎日失禁してデイサービスのトイレの扉を壊し弁償も。 4月の緊急事態宣言を受け、これまで通っていたデイは利用者に「自粛」―自宅でのリモート保育を要請。私たち夫婦はともに介護職で休職できないため、やむを得ず他のデイに通うことに。そこは利用時間が15時までのため、夕方までの時間は移動支援事業を利用することになった。 5月連休明けの休校延長で、息子はさらに不安定になった。移動支援事業で外を出歩くよりも学校の中の方が安全と考え、5月中の分散登校を大阪府教育庁へ要請するファクスを送ったのだが、そのまま学校へと転送されただけだった。 親の意見は届かないのか…と思った矢先、山川会から声がかかり、請願と要請を支援してもらった。 これ以上の長期休校で登校の権利を奪うなの思いを込め、9月入学実施反対、多様な障害への配慮のないオンライン授業反対の請願書を大阪府議会と教育長へ、デイサービスの利用時間の配慮を求めた要望書は、大阪市福祉局、教育委員会、大阪市長へ。 後日、福祉局から事業所へ利用時間の柔軟な対応を提案したとの連絡が入った。 やはり、みんなできちんと手を尽くせば、声が届くんだと思った。 6月ようやく開校し、息子も少しずつ落ち着きを取り戻せたが、長期休校の意味があったのか、と強く思う。「感染を押え込む意味はなかった」との専門家の声も出ている。 どうも知事と市長が大阪を「スーパーシティ」にしたくて、オンライン授業や5G(次世代通信規格)基地局を進めあらゆる身分証明を紐付けする狙いで、今回の休校措置も利用しているのでは、と感じている。 それよりも私たちの声を、要望や請願を聞くことを優先すべきではないのか?  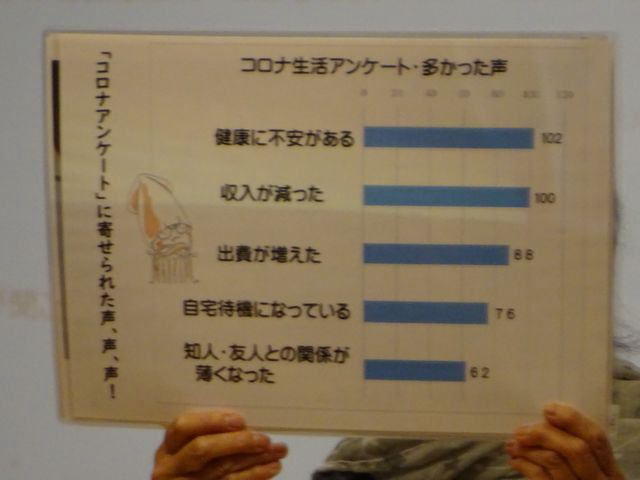 |